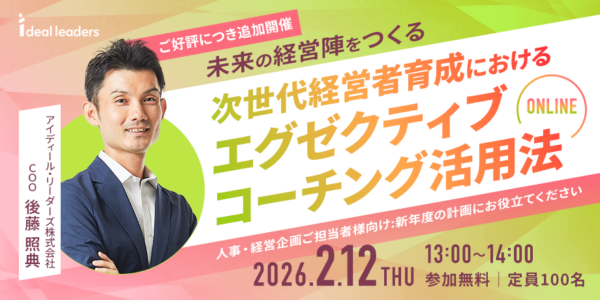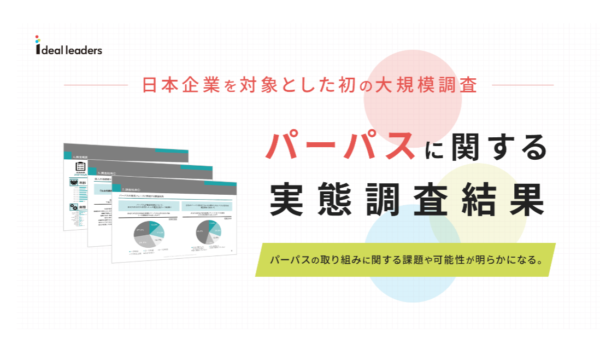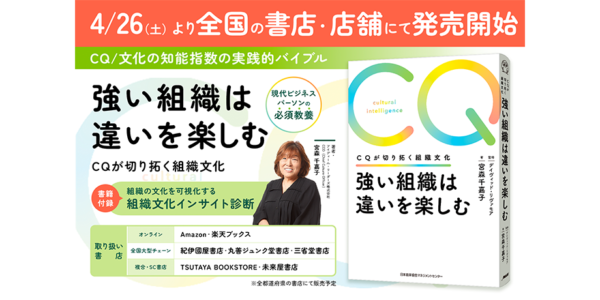組織文化インサイト診断レポート
「組織文化インサイト診断」は、ホフステードの6次元モデルを使い、あなたが所属する組織の文化を可視化するためのセルフチェックツールです。
ホフステードの6次元モデルでは、組織や社会の文化的価値観を6つの次元(軸)から捉えます。
社会と個人の関係性………………………個人主義/集団主義
権力格差(権力/不平等への対応)……階層志向/参加志向
未知への対応………………………………不確実性の回避/不確実性の許容
動機付け要因………………………………達成志向/生活の質志向
時間志向……………………………………長期志向/短期志向
人生の楽しみ方……………………………充足志向/抑制志向
それぞれ両極にある組織の文化は対象的です。しかし優劣や良し悪しはありません。また組織の文化はどちらかに分かれるのではなく、そのあいだで程度の差が表れます。
この診断では12の文化のうち、あなたの回答から“最も顕著に表れた組織の文化”を簡易的にレポートします。CQ(Cultural Intelligence:文化的知性)を高めるヒントとしてご活用ください。
あなたの組織は「不確実性の回避」の傾向が強いようです。
「ルールを守ることを大切にする」「計画・準備を重視しながら物事を進める」といった傾向があるでしょう。入念なリスク対策を講じ、組織を安定的に運営していける文化だと考えられます。
■次元の特徴
・不確実性の回避が強い組織では、計画性や正確性、予測可能性を重視します。曖昧さを減らすために、明確な行動ルールを好む傾向があります。
・物事に取り掛かる際には、過去の事例の確認や情報収集に努めるなど、計画の策定に余念がありません。徹底的に失敗を避けようとするという特徴があるでしょう。
・ルールや手続きを重視するため、柔軟な対応が難しいという側面があります。
・対極にある「不確実性の許容」では、そもそも物事は予測不可能だという見方をします。そのため計画性のある行動やルールづくりに重きを置きません。トライ&エラーで物事を進めようとするため、チャレンジの生まれやすい文化だと言えるでしょう。
■ビジネス上の傾向
・事前にリスクを分析し、対策を講じることで、未知のリスクを最小限に抑える傾向があります。
・「石橋を叩いて渡る」ことで商品・サービスの改善や、安定した組織運営を実現しやすいでしょう。
・その半面、成否が不確かな新しい物事への挑戦には及び腰になることも。「本当にうまくいくの?」「前例はある?」などの意見が往々にして聞かれます。
・手続きを守ることが第一とされ、融通が利かないことから、イノベーションが創出されにくいとも考えられます。
■今後へのヒント
〇フェイルフォワード会議の導入
・個人で抱えがちな失敗や課題をチーム全体で共有し、建設的に活かす、フェイルフォワード(Fail forward)の場を用意します。失敗への寛容度が高まると、新たな挑戦も促しやすくなります。
〇リーダー自身の挑戦と学びの共有
・リーダー自らが失敗を恐れない姿勢を示すべく、挑戦へのコミットメントを明確にします。同時に、ミスや改善点は組織にオープンに共有。またその失敗からの学びをテーマに、メンバーと対話します。心理的安全性と知的誠実性を育むための大事なポイントです。
〇対極のメンバーとの協働
・独断専行で聞く耳を持たないのではなく、相手のやり方を聞き入れる余地があることを示しましょう。
・決めつけるような発言は避け「自分にとっては未知の世界もある」ということを念頭に置くようにしましょう。
<まとめ>
不確実性の回避は、計画性や明確なルールを好むため、品質改善や安定した組織運営に強みを持っています。一方で新しい物事への挑戦はそれほど得意ではないかもしれません。
組織では、不確実性の回避と不確実性の許容の違いによる対立がしばしば見られます。CQ(文化的知性)の視点では、失敗も多いけれどスピーディーにたくさんの挑戦を生み出せるという相手の強みに目を向け、歩み寄ってみることから、違いを乗り越えていきましょう。